点字ジャーナル 2024年2月号
2024.01.25
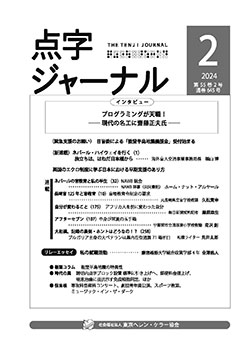
目次
- 巻頭コラム:能登半島地震の特異性
- (インタビュー)プログラミングが天職!―― 現代の名工に齋藤正夫氏
- (緊急支援のお願い) 日盲委による「能登半島地震義援金」受付始まる
- (新連載)ネパール・ハイウェイを行く(1)旅立ちは、はねだ日本橋から
- 英国のエクロ制度に学ぶ日本における早期支援のあり方
- ネパールの盲教育と私の半生(32)NAWB総会
- 長崎盲125年と盲教育(10)盲唖教育令制定の要求
- 自分が変わること(175)アフリカ人を前に変わった自分
- リレーエッセイ:私の就職活動
- アフターセブン(107)中身が常夏の玉手箱
- 大相撲、記録の裏側・ホントはどうなの!?
(258)ブルガリア出身の大ベテランは幕内在位通算71場所目 - 時代の風:踏切内点字風呂多くの設置標準に引き上げへ、
郵便料金値上げ、
喘息治療に抵抗示す免疫細胞同定、
口腔内細菌による血栓症 がん転移を促進、
精神科ウェブ診療でも同効果 - 伝言板:音楽家専攻課コンサート、
劇団青年座公演、
スポーツ教室、
ミュージック・イン・ザ・ダーク - 編集ログ
巻頭コラム:能登半島地震の特異性
元日の午後4時6分と10分の2回起こった地震は、いずれも震源は石川県能登半島の珠洲市内であった。2回目の地震は東京都杉並区の私の自宅でもはっきり感じられたので、その規模の大きさに青ざめた。東日本大震災のときの東京23区の最大震度は5強だったが、それでも私は世界の終わりかと思った。
ところが能登地震は1回目こそ最大震度5強(M5.7)であったが、2回目は最大震度7(M7.6)の凄まじさである。しかも、その後も能登半島では1月6日までに断続的に最大震度5強が6回、6弱が1回起きたのである。
泉谷満寿裕珠洲市長(59歳)は、「市内の6,000世帯のうち9割が全壊、またはほぼ全壊で、壊滅的な状況だ」と被害の深刻さを述べている。
マグニチュード7.6は、熊本地震や阪神・淡路大震災の7.3をも上回り、そのエネルギーは約3倍におよぶ。しかも被災地は豪雪地帯であるため、屋根は雪が流れ落ちるような急勾配にし、瓦をのせて積雪に耐える入母屋造りの家屋が多い。この構造は雪の重さに耐える縦方向への圧力には強いが、逆に大きく横に揺れる動きには、頭が重いので弱い。しかも甚大な被害を受けた地域の耐震化率は輪島市が46%、珠洲市が51%と全国平均の87%に比べて明らかに低い。
北陸地方の中央付近から日本海へ北に向けて突き出た能登半島は、日本海側海岸線で最も突出面積が大きい半島である。しかもこの半島の西の付け根にあたる羽昨市(はくいし)から東の付け根にあたる七尾市に向かって邑知潟(おうちがた)平野が広がる。この平野はほぼ平行する二断層間が陥没して生じた帯状の「邑知潟地溝帯」によって生じた低地である。このため能登半島はこの低地で区切ると山々に覆われた孤島となり、地震により道路が寸断されると、地理的に能登半島の北部にある輪島市や先端に位置する珠洲市への交通アクセスが極めて困難になることがよくわかる。(福山博)
(インタビュー)
プログラミングが天職! ―― 現代の名工に齋藤正夫氏 ――
【2023年12月5日(火)午後、当編集部と石川県小松市のアクセステクノロジーをオンラインで結び、厚生労働省から卓越した技能者(現代の名工)に選ばれた視覚障害者向けパソコンソフトウェア・機器開発販売を手がける(株)アクセステクノロジー代表取締役齋藤正夫氏(75歳)に、世界初日本語スクリーンリーダーVDMの開発に至る道のりなど同氏の半生について語っていただいた。取材・構成は本誌戸塚辰永】
11月13日(月)に現代の名工表彰式が東京都新宿区のリーガロイヤルホテル東京で開催され、被表彰者150人を代表して齋藤正夫氏が謝辞を述べた。
「私は点字を読むのが本当に下手なんです。挨拶を頼まれて家で何度も何度も原稿を読む練習をしてきたのに、リハーサルで読んでいる時にも途中でちょっと詰まってしまって、『困ったなこれ! 本番で恥かくのかな』と思ったんです。ところがいざとなると、最後の本番だけ初めてまともに読めたんです。読んでいる途中で気持ちよくなって大きな声で読めました。その時『俺って本番に強いのかな』って思いました」と表彰式の様子を語る。
齋藤正夫氏は、昭和23年(1948)7月18日、石川県小松市で生まれた。元々弱視であったが、小学校5年生の3学期まで地元の小学校に通っていた。一番前の席に座っても黒板の字がよく見えず、教科書に鼻が擦れるくらい近づけてやっと字が読める程度だった。本来ならばこれほどの視力であれば盲学校で学ぶのだが、昭和30年頃彼が住んでいた地域では盲学校の存在を学校の教師すら知らなかった。
そんなある日、目に怪我をして字が読めない程までに視力が低下し、彼は数ヶ月療養した後、6年生の6月から金沢市にある石川県立盲学校小学部6年に編入した。小松市から金沢市まで30km弱離れており、失明したばかりの子どもが鉄道で通うのは無理なので、寄宿舎での生活が始まった。寄宿舎で生活するには子どもであっても洗濯から掃除まで何でもやらなければならない。ホームシックになった彼は夏休みといった長期休暇が待ち遠しく指折り数えて待った。
親元を離れ寂しい日々を過ごしていたが、盲学校の先輩にステレオアンプやトランジスターラジオや電子回路に詳しい人がいて、感化された彼はそれらに夢中になった。中学生の頃から、友達と書店に行って『電波技術』や『初歩のラジオ』といった雑誌を買ったり、電気工学に関する専門書のタイトルを読んでもらって興味のある本を買っていた、典型的な“オタク”だった。
しかし、電子回路についてはどんなに口で説明されてもわからない。そこは2歳年下の妹が協力してくれた。齋藤氏が高校生の頃、妹が図書館から電子回路の専門書を借りてきて、目次を読んでくれた。彼女は配線図があると、それを点図にしてくれた。父親が建具職人で網戸も作っていたため家には網戸の網がたくさんあった。そこで、網を広げてその上に画用紙を接ぎ合わせた紙を乗せて配線図を書き、それをひっくり返すとギザギザとした凹凸が残る。妹はその軌跡をたどってコンパスの先で細かい点を打って点図にしてくれたのだ。さらに触っても崩れないようにニスを塗ってくれた。そんな妹の協力もあって、電子回路図を頭に描くことが出来たのだった。
齋藤氏は点字を読むのが遅いというがその原因は、小学部6年生から点字を使い始めたこと、真空管アンプやトランジスターラジオ、電子回路を作る電子工作が大好きで小学部6年生から専攻科2年生まで暇さえあればハンダゴテを持っていたことだ。右手にハンダゴテを持つので、部品を保持するために左手の人差し指で抑えているとどうしてもハンダが指先に当たる。ハンダゴテでくっつけるものは金属なので、熱が伝わってくる。「熱いなぁ」と思っても手を離したらハンダがズレるからそこはじっと我慢した。こうしたことを何年も続けていると、左手の人差し指はほとんど炭化状態となり、見た目も黒くなった。左手の指先は温度にも鈍く、感覚も鈍麻しているので、左手で点字が読めない。点字を早く読むには両手読みができることだが、彼は右手でしか点字を読めないのだ。
当時の盲学校教育は、鍼灸マッサージ師に就くことを前提とした教育で、彼も理療科に進んだ。ハンダゴテで左手の人差し指を痛めていたので、鍼を固定する押手の感覚がわからず鍼の実技は落ちこぼれだった。
鍼がとても好きな同級生がいて、「おい、齋藤! 愛知県に鍼の名人がいるから一緒に修行しよう」と言われたが、「俺、嫌だ。卒業したら早くうちに帰りたい」と言って断った。
「彼はクラス一番の出世頭です。アメリカへも出かけて鍼の指導をしたと聞いています」と自慢する。その彼は、東洋鍼学会会長で経絡治療の鍼灸院を神奈川県相模原市を拠点に手広く展開する谷内秀鳳だ。
専攻科を卒業してすぐ開業する人は珍しく、大抵卒業生の治療院で修業したり、整形外科に就職する人がほとんどだった。齋藤氏も実家のある小松市内の整形外科病院に就職した。
アマチュア無線にのめり込む
盲学校は小さな世界でみんな仲間だったが、社会人になると全盲ということもあり、人との付き合いがほとんどなくなり、これではいけないと思った。就職してこづかいもでき、今までやりたかったことを叶えようと、まずはアマチュア無線に挑戦し、24、5歳の頃から勉強を始めた。
盲学校時代は点字も鍼もできず、パッとしなかったが、このアマチュア無線が人生の転機となった。
アマチュア無線は国家資格で、最も簡単な4級の電話級からトライした。試験を受けなければならないことはわかっていたが、どうしたらいいのかわからず、金沢市にある電波管理局に電話して願書を取り寄せた。
試験は口頭試問だったが、元々電気工学が好きだったので、電話級には簡単に合格した。
アマチュア無線の試験は春と秋の年2回ある。次は今の分類では3級の電信級だと思ってその年の秋に電信級を受けた。試験会場に行き、午前中は学科試験。午後は実技でモールス符号の試験で一般受験生と同じ部屋で受験した。
まずモールス符号の聴き取りのテストが始まり、受験生皆がモールス符号を必死に聴いているため教室内は静寂に包まれていた。自分も必死に聴きながら点字板に1文字書き込むと「ゴトン!」とその音が静寂の中で大きく響いた。実際にはそんなに響いていなかったかもしれないが、ものすごく響いたように感じて、その後は一切書けなくなった。そのため、電信の試験で不合格となった。電波管理局に経緯を説明して、次回の試験から受信の試験は別室で受けることが出来るようになった。2回目は不合格だったが、3回目で電信級に合格した。
それならばということで、さらに上の資格を目指したが、1級・2級の上級試験には欠格事由が立ちはだかっており、当時は目の見えない者の受験を認めていなかった。
「人間ってダメだって言われると、なんでってなるんですよ」
3・4級は数百Vの電圧を扱うが、1・2級になると使用する機械が大きくなり2kVや3kVという電圧を扱う。また、電波を出すアマチュア無線は各級別に周波数帯が定められており、そこから逸脱してはならない。自分が出している周波数を見えない人はどのように把握するのか、それがわからないから問題だった。
そこで齋藤氏はアマチュア無線を通じて知り合った仲間に相談して点字で表示される周波数カウンターを自作した。点字の数字は1・2・4・5の点で表すので、1マスに4ピン、5マス分の点字ディスプレイを制作した。こうした機器を使えば周波数を逸脱することはない。電圧は見えなくても注意すれば出来る。そういうことで欠格事由から「目の見えない者」を外して欲しいと全国的な運動に参加し、昭和53年(1978)に受験が認められ、7人が1級試験を受験し、齋藤氏を含む4人が合格した。
「1級っていうのはアマチュア無線でそれ以上上の資格がないので、頑張れば出来るんだと私にとって自信になりました」と齋藤氏は語る。
ということで10mのコンクリート製のアマチュア無線用の柱を自宅に立て、一生涯の趣味にしようとその時は思った。
齋藤氏はモールス信号で世界中の人たちと交信した。交信日時、交信周波数帯などを記録したQSLカード(交信証)を交信相手と取り交わした。それを書くためにカナタイプライターや英文タイプライターを習った。でも、いくら慎重にキーを打っても常にミスタイプをしているのではないかという不安が付きまとった。一旦書いたらそれを確認することが出来ないからだ。そんな中、注目したのがパソコンだった。
パソコンにのめり込む
パソコンを使えばQSLカードを発行したり、無線機を操作する際さまざまな表示を読み取ることが出来るという話が伝わってきた。元々アマチュア無線家は電子工学に興味を持っている人ばかりで、当然早くからパソコンに注目していた。齋藤氏もその1人で、いろいろと情報収集をしていたのだった。
そんな折、東京ヘレン・ケラー協会から『点字サイエンス』が昭和57年(1982)12月に創刊され、齋藤氏は平塚尚一氏(東京都立工業技術センター職員〈当時〉)が創刊号から連載した「講座 やさしいパソコン入門 ― パソコンで何ができるか」を熟読し、パソコンの使い方について概念を学んだ。平塚氏の連載記事を読んで「俺も何とかなるか」と思った齋藤氏は、昭和58年(1983)7月にNEC PC-6001mkⅡというパソコンを思い切って購入した。そのパソコンに決めた理由は、当時一番安かったこと、ゲーム用で貧弱ながらも音声合成機能が搭載されていることだった。
普通パソコンといえばパソコン本体とキーボードそれにディスプレイがセットになっているが、齋藤氏はキーボードとパソコン本体だけをあえて購入した。というのは、自分が入力した文字を人にいちいち確認してもらうことが嫌だったからだ。というのもそれまで電子工学の月刊誌を買ってきては、周囲の人に読んでもらっていた。最初のうちは家族が読んでくれていたが、そのうち「後でね」「明日ね」と言われるようになり、それが続くとイライラが募った。
アマチュア無線のQSLカードを自力でタイプライターで書いていたが、それに代わるものとしてパソコンを買ったのに人の目を借りてディスプレイを確認してもらうようでは本末転倒である。最初はキーボードを操作しても何も反応がなかった。そこでパソコンに詳しい人に聞いたり、自分の持っている情報でプログラミングをパソコンに入力していった。もしうまくいけば目的の結果が得られる。だが、途中でエラー音が鳴ると、それは入力ミスがあったか、プログラムに間違いがあったかだ。エラーがあればどういうエラーか目で確認できるが、齋藤氏にはそれがわからない。エラー音が出たり、何も反応がなかった場合まず疑うのはミスタイプだ。彼はプログラムを記憶していたので、目的の結果が出るまで最初から入力をやり直した。短いプログラムならそれでもよかったが、段々複雑なプログラムを入力するとなると、長いものだと点字4ページ分にもなった。それを1字1句間違いなく入力するという挑戦が続いた。
スクリーンリーダーに挑戦
齋藤氏は、コンピューターが立ち上がる際にディスプレイに文字が出るからこれはコンピューター自身が文字をディスプレイに出力しているのだと思った。それならば、ディスプレイに出ている文字を同時に音にしたらもっとパソコンを便利に使えるのではないかと思い模索した。
当時のパソコンは8ビットで、ワープロならワープロ、表計算なら表計算の作業しかできないシングルタスクというものだった。ディスプレイに表示される文字と同時に音が出るようにしようという発想はあったが、これはシングルタスクから同時に複数の作業をさせるマルチタスクに置き換えることを意味した。そのためにはCPU(中央演算処理装置)に直接命令を出すマシン語を習得する必要があり、その勉強を始めた。マシン語については理屈ではわかっていたが、マルチタスクに対応させるためにはかなり越えなければならないハードルがあった。
最初のうちは手探りでマシン語をパソコンに入力し続けた。周囲にマシン語を教えてくれる人もいなかったので、ただの1度もディスプレイを見てもらうこともなく独学で習得した。そうした苦労の甲斐があって、パソコン購入から5か月後の昭和58年(1983)12月に世界初日本語スクリーンリーダーが誕生した。
「キーボードをたたくとリアルタイムで音が出るんですよ。パソコンってこんなに便利なものなのか。あの時の喜びって表現のしようがないな」と齋藤氏はしみじみ振り返る。
だが、まだ音声合成装置が貧弱で「宇宙語」のように聞こえてよくわからなかった。その上反応がじれったくなるほど遅くとても使い物にはならなかった。そこで、齋藤氏は、モールス符号なら1分間に約100文字程度は聞き取ることができるので、モールス符号を使ったプログラムを書いて使用していた。
その話を聞いた知人が「世の中にはもっと性能のいい音声合成装置が市販されているから、それを使ってやってみないか」と言ってくれた。「そんな高いものを買うお金はない」と齋藤氏は断ったが、「私がそれ買うからやってよ」と言われ、その言葉をありがたく受け入れた。そこで、パソコンから外部の音声合成装置に出力するプログラムの作成に着手し、明確な音が出るようになった。
パソコンが進化するにつれ、音声合成装置もより音質が良いものが発売された。新しいパソコンや音声合成装置への対応が面白くなって、人からも頼まれるようになった。齋藤氏が始めたころはBASICで半角のアルファベットとカタカナしか対応していなかったが、同じBASICでも全角文字が使えるようになり、ひらがなや漢字が使用できるようになった。そのうち基本ソフトがBASICからMS-DOSになると完全に漢字カナ交じり文に対応するようになった。
最後まで齋藤氏を悩ませたのが、漢字の読みだった。文字を音で表現することは容易ではなかった。入力した文字がディスプレイに表示され、それを捉えて読み上げる。特に、同音異義語の読み分けをさせるのには苦心した。
単漢字読みでは、第1水準約3000文字と第2水準約3400文字の読み方を一つ一つ齋藤氏自身で考え出した。例えば、「上(うえ)」は「上下(うえした)の上(うえ)」といった感じだ。そして、表示される漢字を熟語として全部探って読むようにする作業に取り掛かった。これが切りがないという。スクリーンリーダーが進化した今でさえ誤読することも時々ある。開発した当初変な読み方をしたらその都度プログラムを書き換えて正しい読み方に更新した。
また、ディスプレイ上でカーソルを移動する際にどういう読み方をしたらよいのか。横に移動した時は1文字ずつ読む。上下に移動した時は1行ずつ読む。漢字の読み方としては1文字ずつの読み方と熟語としての読み方、送り仮名を含めての読み方というように何通りもある。
音声読み上げというものはなかなか厄介なもので、パソコンの作業中に知りたい箇所が分かれば、そこで音声が止まればいい。そのあとの情報はユーザーにとって無駄である。1行全部だらだらと読み上げてしまうようではスクリーンリーダーとしては役に立たない。そのあたりの問題を齋藤氏は解決し、MS-DOS用スクリーンリーダーVDM100を昭和62年(1987)に完成させ、視覚障害者の注目の的となった。ちなみに、VDMとはヴォイス・ディスプレイ・マネージャーを略したものだ。
「私はスクリーンリーダーを人のために作ったんじゃなくて自分がパソコンを使いたいと思って作ったんです。そしたら、全盲の齋藤が使っているのなら俺たちも使いたいっていうことで自然に広がっていったんですね」と齋藤氏は苦笑いする。
それから「一般のソフトウェアでも音が出るんだったら使えるはずじゃないか」というユーザーからの期待が高まった。だが、実際ディスプレイ上に表示されている文字情報と音声で聴いている情報がずれていることもあった。そこで齋藤氏は日本語ワープロソフトウェアの「一太郎」、表計算ソフトウェアの「ロータス1-2-3」をVDMを用いて使用できるよう工夫した。
MS-DOSの頃、いろんな人が齋藤氏が開発したVDMを使用して視覚障害者が使えるソフトウェアが次々と世に出た。これによって、視覚障害者がメールを使用したり、インターネットにアクセスできるようになった。
その後ウインドウズ95が発売されると、時代はMS-DOSからウインドウズへと変わっていった。それと共に、視覚障害者自身がソフトウェアを容易に開発できなくなり、齋藤氏が開発したスクリーンリーダーの開発は(株)高知システム開発に引き継がれた。だが、齋藤氏が築き上げたスクリーンリーダーの基礎は今なお脈々と引き継がれている。
改めて我々が今こうして仕事や余暇でパソコンをあたりまえのように使用しているのには齋藤正夫氏の飽くなき好奇心と努力があったからこそだ。
齋藤さん現代の名工受賞おめでとうございます。
編集ログ
11月16日~12月3日の旅程でネパールに出張しました。
これまでネパール国内の移動には、トヨタ・ランドクルーザー(ランクル)を使っていました。ところが2022年の11月、インド国境沿いの町ビルガンジ(人口26万8,000人)で、このランクルが時速60kmを超えると激しく振動するようになりました。
日本から送って31年目だったので、帰国後専門家に聞くと、部品さえあれば修理できるが、30年を過ぎたら部品がない可能性が高いと言ったので、修理は諦めました。
ドイツと日本の車のエンジンは30年を過ぎてもビクともしないが、インド製は5年を過ぎると途端に馬力が弱まると言ったのは、ネパールのプロドライバーです。そこで、今回のネパール出張で、4日間ドライバー付4WD(インド・マヒンドラ製スコルピオ)を1日1万5,000円でレンタルした際は2020年モデルであることを念押ししました。
何しろ車両取得税が200%かかる国なので、車の価格はとても高いのです。車両本体価格が200万円とすると、税金は400万円かかるので、合計600万円という価格です。
このためネパールではサイクルリキシャ(自転車の後ろに二人乗りシートがついた三輪車)、オート三輪タクシー「テンプー」、タクシー、ホテルタクシー、路線バス、そして中国製EVのミニバンタイプEC36の乗り合いバスを活用しました。
EC36はフル充電でどれだけ走れるのかとても気になりました。私たちが4時間かかったチャリコット、カトマンズ間は約130kmあるのですが、途中で充電したということは、その距離を余裕を持って走るだけの自信はないということなのでしょう。
私たちがネパールの辺境部を4WDで走る場合は、ガソリンスタンドがないので、別途、燃料を持参します。今回の旅でもお湯も出ない暖房もないホテルという名のロッジで、ドライバーが10L缶を持ち上げて車に軽油を補充していました。
EVの場合はそれはできないので、長距離走行にはちょっと無理があるように思いました。(福山博)

