点字ジャーナル 2023年10月号
2023.09.25
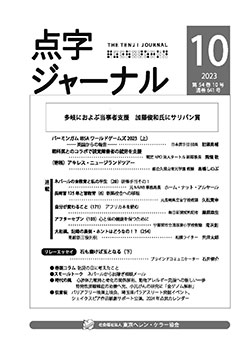
目次
- 巻頭コラム:防災の日に考えたこと
- 多岐におよぶ当事者支援
加藤俊和氏にヘレンケラー・サリバン賞 - バーミンガムIBSAワールドゲームズ2023(上)
―― 英国からの報告 - 眼科医とのコラボで視覚障害者の就労を支援
- (寄稿)アキレス・ニュージーランドツアー
- スモールトーク ネパールから出稼ぎ相談メール
- ネパールの盲教育と私の半生(28)研修手当その1
- 長崎盲125年と盲教育(6)新築校舎への移転
- 自分が変わること(171)アフリカ本を読む
- リレーエッセイ:石も磨けば玉となる(下)
- アフターセブン(103)心と体の健康を保つために
- 大相撲、記録の裏側・ホントはどうなの!?
(254)高齢新三役列伝 - 時代の風:乳がんの発生と変異発症の過程解明、
動物アレルギー克服への新しい一歩、
特発性肺線維症の治療へ光、
小児がんの研究に「全ゲノム解析」 - 伝言板:バリアフリー映画上映会、
埼玉県パラアスリート発掘イベント、
シェイクスピア作品観劇サポート公演、
2024年点図カレンダー - 編集ログ
巻頭コラム:防災の日に考えたこと
1923年9月1日に発生した関東大震災にちなみ、「9月1日は『防災の日』」である。このため、同日には各地で防災訓練が行われ、当協会も例外ではない。
コロナ禍の最中は消防署から署員を派遣してもらうこともなく、手短に片付けていた。そして今年は4年ぶりに以前のように実施されたので、私にとっては最後の防災訓練でもあり新鮮だった。だが、担当から外れたせいで訓練を客観的に観察できたこともあり粗も見えた。そこで感じた課題は、どこまで実際の地震や火災を想定しているかということだ。
たとえば計画では1次避難場所はヘレン・ケラー学院前になっているがこれは適当か。実は20年ほど前までは、点字出版所の1次避難場所は早稲田別館前で、そこで点呼もとっていた。その後、ヘレン・ケラー学院前で合流し、消化訓練などを行う手筈だった。ところがその事情を知らない学院前に陣取った20年前の消防署員が、「集合が遅すぎる」と激怒した。それに対してきちんと説明せずに、翌年から点字出版所の職員も1次避難場所をヘレン・ケラー学院前に変更してお茶を濁して今日に至っている。
だが、実際に東日本大震災が起きた時、出版所の職員は早稲田別館前から一歩も動くことはなかった。2次避難場所の戸山公園の様子を探るため先遣隊を派遣したが、動かない方が安全だろうという結論だった。
今年の訓練では4人の消防署員が手分けして、避難訓練にも立ち会った。このため講評では、「別館前と学院前の二手に分かれての避難だった」と、現状もよく理解していた。このため来年からは点呼までも別館前で行うようにした方が実情に即しているのではないだろうか。
このような齟齬は当協会ばかりではないだろう。訓練のための訓練でなく、実際に想定される災害に対応した訓練でなければ意味はないし、逆に危険な場合さえあり得ると宮城県石巻市大川小学校の震災遺構などは教えている。(福山博)
多岐におよぶ当事者支援 加藤俊和氏にヘレンケラー・サリバン賞
【本年度の「ヘレンケラー・サリバン賞」は、日盲委評議員(災害担当)で、視覚障害者の歩行の自由と安全を考えるブルックの会代表、点字楽譜利用連絡会副代表など点字、移動、災害など視覚障害者に関わる多方面で活躍する加藤俊和氏(78歳)に決定した。
第31回を迎えた本賞は、「視覚障害者は何らかの形でサポートを受けて生活している。それに対して視覚障害者の立場から感謝の意を表したい」との趣旨で、当協会が委嘱した視覚障害委員によって選考される。
贈賞式は10月4日の開催を予定している。本賞(賞状)と副賞として、ヘレン・ケラー女史直筆のサインを刻印したクリスタルトロフィーが贈られる。以下、敬称略。取材・構成は本誌 雨宮雅美】
加藤俊和は1945(昭和20)年3月25日、京都市西陣のビロードを扱う織屋の家に生まれた。幼少期は母親が産後の病気で母乳が出なくなったことや終戦間もないため栄養失調で虚弱体質となった。小学校でも休学が続き、いじめにもあった。中学生に上がる頃になると最初の不況を迎え、家業は急速に傾いた。
中学・高校時代は貧乏のどん底だったが逆に体は丈夫になった。奨学金を得て京都府立山城高校へと進学。自分自身がかつて病弱だった体験から何らかの役に立ちたいという思いも重なって青少年赤十字の活動を始め、養護学校への慰問などを行う傍ら点字に巡り会い、点訳活動にも没頭した。1962年には京都にも点訳奉仕団をという日赤京都の職員とともに広く呼びかけて「京都赤十字点字友の会」を結成した。当時は特に点字のマニュアルもほとんどなく、自分で調べながらであった。
鳥居篤治郎(とりい とくじろう)から薫陶を受ける
そのような中で、運命的な出会いがあった。点訳をはじめて間もない1961年の春に京都ライトハウスができ、近かったこともあって、何も知らずに点字図書館にのこのこと出かけたのである。そこで出会ったのが、加藤が最も影響を受けた鳥居篤治郎その人だった。鳥居は、岩橋武夫とともに大正期から日本の盲界を支えてきた大御所であり、武夫亡き後の日本盲人会連合の2代目会長として全国的な活動をしながら念願の京都ライトハウスを設立していた。加藤は、そのような偉い先生とはつゆ知らず、点字図書館にいた鳥居に何やかやとたずね続けた。鳥居は忙しいはずなのに、何のゆかりもない一高校生に、ていねいに応えていただいたと加藤は語っている。そんな中、ある日「ちょっと話し相手に行ってくれるか」と軽く依頼されたことがあった。それは失明後2年ほどの中途失明者宅の訪問であった。だが当然ながら、何も知らない少年が行っても話し相手にもならなかった。そのとき加藤は、これまで想像していた盲人とは異なる中途失明者の存在に気づかされた。当時は大多数の全盲者の生活に直結する三療関係や新職業、年金等の問題が山積しており、中途失明者のことまでは手が回っていなかった。
加藤は、このことによって、点字が読めず何の支援も受けられず、何よりも絶望のまっただ中にいる中途失明者がいること、そして話すことすら出来ない自分に愕然としたと語っている。鳥居に、何か刺激を受ければ、との意図があったかどうかはさておき、このことが加藤にとっては大きな刺激となり、後々の様々な支援活動への大きなきっかけとなったできごとであった。
ものづくりが好きだった加藤は、国立京都工芸繊維大学の電気工学科へ進学。父親も亡くなり実家もなくなったため寮に入り、自分の生活費から学費まで家庭教師で稼ぎながら、学業にも励んだ。また、男声合唱団に入って指揮者として活動した。このことが、後の点字楽譜への本格的な活動につながっていった。
1968年に立石電気(現・オムロン)の研究所に就職。赤外線関係などの開発業務に12年間従事した。その間、業務を超えて、点字自動製版機の開発や超音波ケーンの開発等にも関わっている。その昼休み時間に、自分のメモとして『点字毎日』の記事のほしい部分のみをときどき墨訳していたが、そのうちに記事の内容を分類し、同じ種類の記事をまとめて墨訳を行い、貴重な情報源として中途失明者の復職運動をはじめ様々な活動の資料として役立てたりもした。
1970年代後半からは、日本点字委員会の活動に点字数学・理科記号など、ボランティアとして加わっていった。当時は様々な分野で技術の専門家が求められ始めていた時代でもあり、日本ライトハウスの常務理事であり日本の点字出版界の牽引役でもあった宮田信直から誘いを受けた。しかし、苦学生を経て“多忙な看護婦の夫”となり小さい子供たちもいる生活のこともあり、給料に差のあった福祉の世界に飛び込むのに2年を要した。
福祉の世界へ
1980年、加藤は業界で最初に点字自動製版機が本格的に導入されるのと同時に日本ライトハウス点字出版所に転職した。以降、その本格的な利用によって、点字出版業務の拡充と安定化を図るとともに点字情報技術センターの新築を実現し、その所長となった。施設を超えた活動も多く、「点字本の価格差補償制度」については、各点字出版所と協力してその中心役となり厚労省との細かい折衝も重ねてその実現に貢献している。
1997年からは日本ライトハウスの常務理事兼視覚障害リハビリテーション所長に就任し、高齢者リハへの対応など大きく変化しているリハ関係の課題にも真っ正面から取り組み、歩行訓練士の国家ライセンス化を目指して、厚労省とも度重なる折衝を続けるなど精力的な活動を続けた。しかし、明確な成果を得るまでには至らなかったことに悔いが残る、と加藤は語っている。
2002年、加藤は日本ライトハウスを去り、加藤のボランティア活動の出発地でもあった鳥居篤治郎の思い出深い京都ライトハウスに点字図書館長として着任した。その後に情報ステーション所長として7年勤務し2010年に定年退職した。
その後は現在に至るまで、視覚障害者関連の多岐にわたる支援事業にボランティアとして精力的に関わり続けている。
点字楽譜への取り組み
加藤は、1970年代から半世紀にわたって、数学・理科、点字楽譜、触図など、専門分野の点字の第一人者として取り組んでいる。特に加藤は、「日本の点字楽譜全般を支え続けている」と言われている。
高校在学中にコーラスもしていたが、大学で男声合唱団に入って指揮者となり、短期間ではあるが、後の大阪芸術大学名誉教授の桜井武雄から直接教えを受けたこともあった。
加藤は、1970年に京都府立盲学校の理療科教員でテノールの林繁男と巡り会った。1954年のパリ国際点字楽譜会議に参加していた鳥居と林はその記録の英語版を翻訳し1963年に『世界点字楽譜解説』の点字版を出版した。加藤は1972年の墨字版出版に関与し、点字楽譜に本格的に取り組むきっかけとなった。
ところで、日本ライトハウスは日本で唯一、盲学校用小中高の点字音楽教科書を発行している。教科書においては、「図のような五線譜をどのような点字楽譜のレイアウトにするか」が非常に重要とされている。1981年から編集を全面的に担った加藤は様々な生徒たちに分かりやすい点字楽譜レイアウトを工夫して点字教科書としての統一を実現した。これが「様々な生徒に適した点字楽譜レイアウト方式」であると評価され、以後40年以上にわたって継承されている。また1984年文部省発行の『点字楽譜の手引き』の実質的な全体編集者として発行に寄与した。
一方では、38年ぶりの点字楽譜国際会議に、日本点字委員会から日本代表として参加した。この会議は、長年の冷戦で東欧と西欧に分断されていた点字楽譜記号の再統一を計る歴史的な会議であった。
なお、日本語の性質を含めて、日本における点字楽譜表記の実質的なまとめ役を担ってきた加藤は、その独自性も踏まえて点字楽譜の教科書表記や一般表記など各種マニュアルの準備を進めるかたわら、増加している中途視覚障害者への点字楽譜の理解を広げるために講習会を開催するなど、点字楽譜全体の幅広い普及活動に精力的に取り組んでいる。
災害支援の先頭に立つ
加藤といえば東日本大震災時の災害支援の功績を語る人は多い。加藤は、災害時には、「つながりのある人への支援」とともに、「つながりのない大多数の中途視覚障害者をそのままにしておけない」という切なる気持ちが支援を支えていると言う。
加藤は、阪神・淡路大震災の時にも災害支援の経験をしている。当時、日本ライトハウスの情報部門の長であった川越利信が結成した災害支援団体「ハビー」によるボランティア活動が注目されたが、そのとき大阪で後方支援に当たっていた。被災した神戸や阪神地区には日本ライトハウスの情報部門やリハ部門の利用者が多く、個人情報の扱いもまだ緩く被災者の把握がしやすかった。しかし、組織のあり方や行政との連携など課題も多いことを経験していた。
2011年、東日本大震災が起こったとき、自分しかできないことがあることを感じていた。それは、広い範囲の被災視覚障害者をどれだけ救済できるのか、だった。阪神・淡路大震災では可能だったことが、東日本大震災ではまったく役に立たないことを肌で感じていたのである。環境が激変した視覚障害者にとっては、歩行訓練士をはじめとする視覚リハの専門家の支援が急務となっている。しかし、点字図書館利用者であっても、東北の各点字図書館は県立となっていて個人情報に厳しく、避難所をまわっても当事者が声を上げないために見つからない、と予想された。そのようなときの支援体制基本は、鳥居篤治郎にあった。鳥居は1956年に、当事者・福祉界・教育界の3分野にまたがる「社会福祉法人日本盲人福祉委員会(日盲委)」を結成し、各省庁へ強く働きかけていた。そして、点字郵便物の無料化をはじめ生活に根ざした各種の要求などに大きな成果をあげていた。
それでも、災害支援のような様々な分野にまたがる活動においては、日盲連や日盲社協よりも日盲委のような幅広い組織が最適であると加藤は考え、関係者を説得した。そして、自らボランティアの事務局長として、厚労省から各自治体や現地を駆けずり回った。
この東日本大震災では被災者1455人もの方々が日盲委に支援を求めてきたが、1・2級の手帳を持つのに、音声時計を知らない人が43%もいたことを加藤は訴え続け、情報伝達の大きな改善を求めるきっかけにもなった。
加藤は、そのほかにも復職支援やホームの安全、踏切の安全などの環境整備関係、読書権保障に関わることなど、多岐にわたって様々な活動に深く関わっているが、大切にしていることは、やはり鳥居から学んだように、いくつかの分野を連動させて、できる限りワンストップで支援が得られ継続していくことであると言う。
あらためて視覚障害者に寄り添いつづける理由を加藤はこう語る。
「その人の気持ちになりたいというだけです。そのときそのときを想像して、ちょっとでも何かできないかと思うだけです」
謙遜する京言葉のはんなりとした印象とは裏腹にその信念の強さが今も加藤を動かし続けている。
編集ログ
2011年3月11日の東日本大震災の津波で、宮城県石巻市立大川小学校の児童・教職員84人が死亡・行方不明になりました。地震から津波まで50分の猶予があったのに多数の犠牲が出たのにはいくつかの要因があります。その一つは、同校の校庭が1次避難場所となっており、2次避難場所は「近隣の空き地・公園等」と曖昧なまま記載されていたことです。
仮に「2次避難場所は裏山」と特定されていたら、犠牲者は出なかったでしょう。しかし、大川小学校付近で石巻市の広報車が津波の接近を告げ、高台への避難を呼びかけていたのにもかかわらず、同校は避難先を津波の方向にある標高6~ 7 mの北上川堤防付近に定めました。そして教職員と児童らは地震発生から40分以上たってから全員徒歩で向かい、津波に遭遇して、最後尾にいた教職員と児童だけが流されそうになりながらも裏山に登ってからくも助かったのでした。
当日は降雪により裏山は足場が悪く、未曾有の大地震直後のため土砂崩れ、地盤沈下、倒木・落石などの可能性も考えられることからそこへの避難をためらったのです。そればかりか裏山に勝手に避難していた児童を叱りつけて連れ戻しさえしました。
また、熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」は、2020年7月4日の九州豪雨で濁流にのみ込まれ入所者14人が犠牲になりました。
1階にいた入所者70人を2階にあげる垂直避難は、エレベーターがないので、車椅子ごと運ぶため4人での作業となりました。40人ほど上げたところで水が入ってきたので、テーブルを並べてその上に車椅子ごとのせました。しかし、その時点で車椅子を諦め、一対一でおんぶして垂直避難したら犠牲者はでなかったでしょう。
裏山で転ぶことを心配しすぎたり、生死にかかわる緊急事態であるにも関わらず入所者を丁寧に扱おうとする日本人の完璧主義とその裏腹なリスクマネージメント下手が、このような悲劇になることもわれわれは肝に銘じたいものです。(福山博)

